院長ブログ
2025.07.30
小説「国宝」を読んで
世間というのはどうしてこうも二世が好きなのだろうか?それは期待される成功物語の続編を見せてくれるからだ。競馬だって有名な父の子を買ってしまわないか。勝ち馬に乗る、そんな安心感があるということだ。
ところが、二世の中には一定の確率で”バカぼん”も含まれていて、世間はこれを嫌う傾向にある。”カエルの子はカエル”という血への信頼と”バカぼん”という裏切りを併せ持つのが小説「国宝」の俊介(俊ぼん)だ。歌舞伎の家に生まれ、サラブレッドとして何の苦労もなく育つが、1回大役を身分違いに奪われただけで家出してしまう。なんと10年も。まさに、由緒正しい”バカぼん”だ。
一方世間は”たたき上げ”も好きだ。立身出世物語の結晶「おしん」は山形の貧乏小作からスーパーを経営するまでに至った”たたき上げ”女性の話で、最高視聴率62.9%は、いかに世間が”たたき上げ”物語が好きか、ということだろう。やくざの子から人間国宝までになった喜久雄は”たたき上げ”代表だ。
”たたき上げ”は叩かれてなんぼ。叩かれないと世間というか物語として受けないので、喜久雄は辛酸をなめ尽くす。師匠でもある俊介の父親(二代目花井半次郎)が死んでしまうので、後ろ盾が無くなり、歌舞伎でもセリフの無い端役しかやらせてもらえない。私の好きな二代目中村吉右衛門(鬼平)は養父だった実の祖父が亡くなった後、それまで「ぼん、ぼん」とかわいがられていたのが、楽屋を追い出され周りが冷たくなった話を自伝で書いていたから、こういう社会的いじめは公然なのだろう。それもこれも「芸の肥やし」か。しかし「芸の肥やし」っていじめも隠し子も吸い込んでくれる、ブラックホールみたいな言葉だな。
話がそれたので元に戻すが、俊ぼんはスーッと帰ってくる。10年逃げていたのに氷の上を滑ってくるように摩擦係数0で元に戻ってくる。”バカぼん”というマイナスも、”改心”という重力変換装置が効いてしまえば、マイナスがプラスに転じる。”判官びいき”という弱い立場の者への同情心は多くの人にあるものな。
一方喜久雄は”バカ”がとれた”ぼん”が戻ってきたので歌舞伎界を追い出される。師匠の残した借金や部屋弟子たちの給金をまかなってきたのは喜久雄なのに。それもやりたくないような映画や地方巡業の仕事をして。
本当の判官は喜久雄じゃないの?と私は喜久雄びいき。だって映画にも使われた「一番欲しいの、俊ぼんの血ぃゃわ」で、開業したころの「病院の2代目に生まれたらこんな苦労はせんで済んだのに」と考えた自分を思い出したもの。
さて、喜久雄は歌舞伎の世界に戻り、「ただ芸に生きてきて、ただ芸に生きたい」と邁進する。芸を極めれば極める程、舞台という虚構の世界と、現実の一線があやふやになり、あっち(虚構)の世界に浸りたいとゆっくり正気を失っていく。
何かに集中することが芸で、それを披露するのが舞台なら、ありとあらゆる最小単位は誰でも持っていると思う。舞台にせり上がる瞬間は、家を出るときのサラリーマンもいれば、エプロンを締めたときのシェフもいるだろう。私だったら白衣を着た時か。
「国宝」は私の芸魂を刺激してくれた。コロナ禍の頃「鼻の検査を限界まで痛くないよう極めよう」と考えていたことを思い出し、ここ最近またコロナが流行しているので、この芸に精進している。
綿棒が通る鼻道は千差万別で同じ人でも時間によって変わってくる。視覚は入口では有効だが、ほとんどは手の感覚だけが頼りだ。なんか書けば書くほど、私の小者感が強調されていく。。。でもね、数日前「この子は鼻の検査はこの病院でしかやらない!というんですよ」と親御さんに言われたよ。
ーごひいき筋の誕生だ!
喜久雄と私が違うのは、私はこっち(現実)に留まり芸(ちっちゃいが)を極めている。ということだ。
そして物語は、もうこっちに戻れない、完全にあっちに行ってしまった喜久雄が国の宝となって幕が下りる。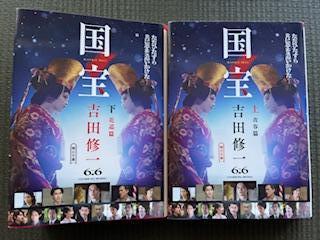
(文庫本で上下2巻)
夏休みに入るのでしばらくブログはお休みします。夏休みはあっちなのか?こっちなのか?

